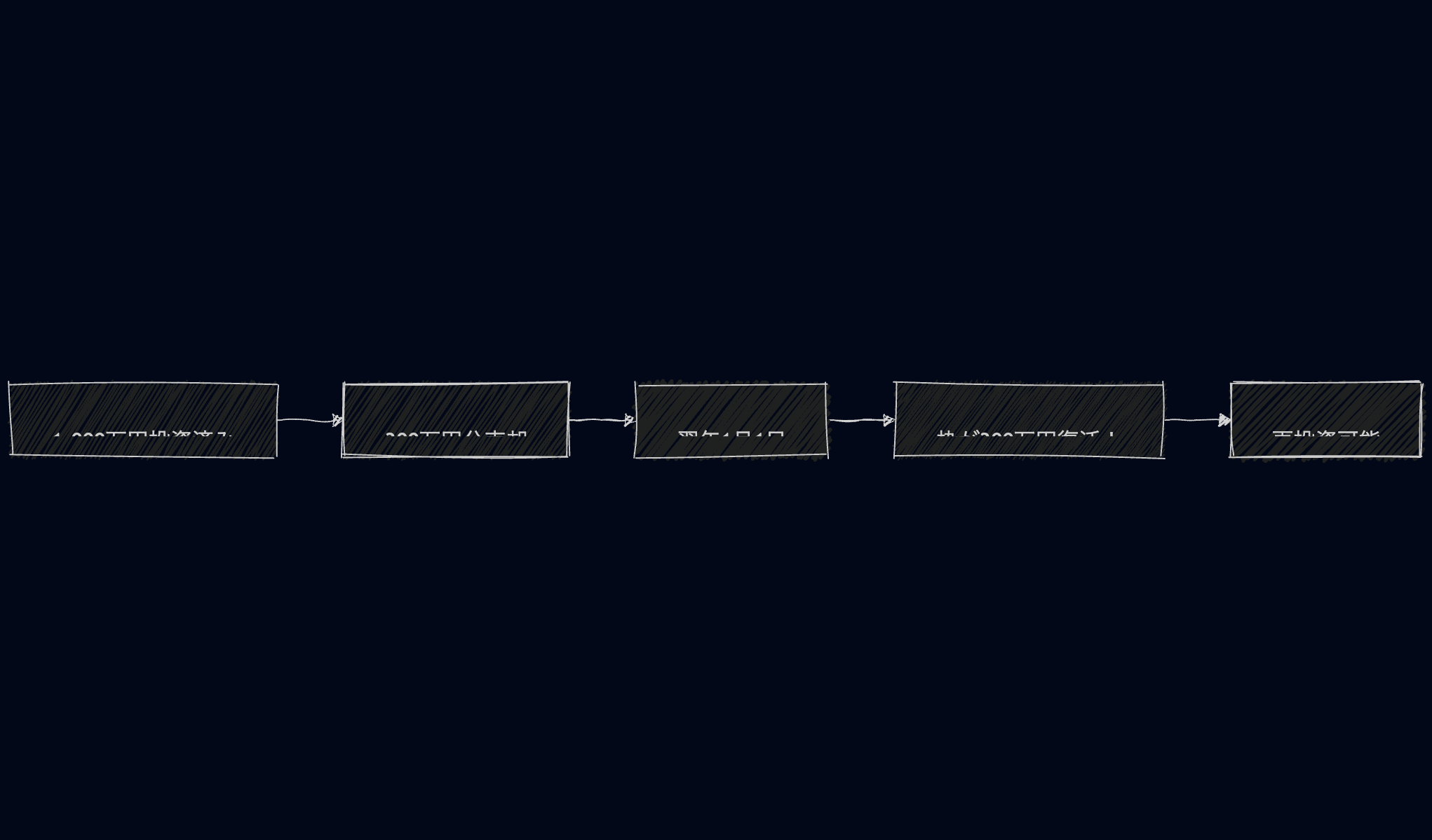はじめに 新NISAの「1,800万円」を完全理解する
「新NISAの1,800万円って、生涯で投資できる上限なの?」 「売却したら、その枠は二度と使えない?」
いいえ、違います!新NISAの非課税保有限度額は、売却すれば枠が復活する画期的な仕組みなのです。
本記事では、この複雑な制度を図解を交えて分かりやすく解説し、あなたの資産運用を最大化する方法をお伝えします。
第1章 非課税保有限度額の基本構造
1.1 1,800万円の内訳
新NISAの非課税保有限度額は1,800万円ですが、その内訳には重要なルールがあります。
【非課税保有限度額の構成】
総枠:1,800万円
├── つみたて投資枠:1,800万円まで使用可能
└── 成長投資枠:最大1,200万円まで
※両枠は併用可能
1.2 年間投資枠との関係
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 360万円 |
| 保有限度額 | 1,800万円 | 1,200万円 | 1,800万円 |
| 最短到達年数 | 15年 | 5年 | 5年 |
ポイント 年間360万円フル活用なら、最短5年で1,800万円に到達!
第2章 簿価残高方式の仕組み
2.1 簿価残高とは?
新NISAでは「簿価残高方式」で枠を管理します。
簿価残高 = 購入時の金額の合計(取得価額)
※現在の評価額(時価)ではない!
2.2 具体例で理解する
ケース1:値上がりした場合
【投資】100万円で株式購入
↓ 2年後
【評価額】150万円に値上がり
簿価残高:100万円(変わらず)
使用枠:100万円
残り枠:1,700万円
ケース2:値下がりした場合
【投資】100万円で株式購入
↓ 1年後
【評価額】70万円に値下がり
簿価残高:100万円(変わらず)
使用枠:100万円
残り枠:1,700万円
重要:評価額が変動しても、使用枠は購入時の金額で固定!
第3章 売却時の枠の復活メカニズム
3.1 枠の復活ルール
新NISAの最大の特徴は、売却すると翌年に枠が復活することです。

3.2 復活のタイミングと計算
| 売却時期 | 枠の復活時期 | 注意点 |
|---|---|---|
| 2025年中 | 2026年1月1日 | 年内は復活しない |
| 2025年12月31日 | 2026年1月1日 | 年末売却も翌年復活 |
3.3 実践例 リバランスへの活用
【2025年】
保有資産:1,800万円(枠フル使用)
├── 株式:1,200万円(評価額1,500万円)
└── 債券:600万円(評価額550万円)
【リバランス実行】
12月:株式を300万円分売却(簿価ベース)
【2026年】
1月:枠が300万円復活
→ 債券に300万円再投資してバランス調整
第4章 成長投資枠の1,200万円制限
4.1 なぜ1,200万円なのか?
成長投資枠には独自の上限があります。
| 投資枠の種類 | 保有限度額 | 対象商品 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠のみ | 1,800万円 | 金融庁指定の投資信託 |
| 成長投資枠のみ | 1,200万円 | 株式、投資信託、ETF等 |
| 併用 | 1,800万円 | 両方の商品 |
4.2 効率的な枠の使い方
パターン1:安定重視型
つみたて投資枠:1,200万円(インデックスファンド)
成長投資枠:600万円(高配当株)
合計:1,800万円
パターン2:成長重視型
つみたて投資枠:600万円(全世界株式)
成長投資枠:1,200万円(個別株・ETF)
合計:1,800万円
パターン3:つみたて特化型
つみたて投資枠:1,800万円(各種インデックス)
成長投資枠:0円
合計:1,800万円
第5章 よくある誤解と注意点
5.1 誤解1:「1,800万円投資したら終わり」
誤解:生涯で1,800万円しか投資できない
正解:売却すれば何度でも再投資可能
【生涯投資可能額の例】
30歳から70歳まで40年間運用
・1,800万円投資
・10年ごとに全売却→再投資を繰り返す
→ 実質7,200万円以上の投資が可能!
5.2 誤解2:「利益が出たら枠が増える」
誤解:1,000万円が2,000万円になったら、枠も2,000万円使用
正解:簿価は1,000万円のまま
5.3 注意点:枠の復活は翌年
年内に売却→再投資のサイクルは不可能です。
【NG例】
6月:500万円投資
8月:全額売却
9月:また投資したい → ❌できない(翌年まで待つ)
第6章 FP視点での活用戦略
6.1 ライフステージ別活用法
20〜30代:積極運用期
・年間360万円フル活用
・成長投資枠で個別株にチャレンジ
・つみたて投資枠で全世界株式
40〜50代:バランス調整期
・定期的なリバランス(売却→再投資)
・成長投資枠で高配当株
・つみたて投資枠でバランスファンド
60代以降:取り崩し期
・必要分だけ売却
・翌年の枠復活で再投資
・相続対策として活用継続
6.2 iDeCoとの併用戦略
| 制度 | 新NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 目的 | 中長期の資産形成 | 老後資金特化 |
| 引き出し | いつでも可能 | 60歳まで不可 |
| 節税効果 | 運用益非課税 | 掛金も所得控除 |
| 優先度 | 流動性重視なら◎ | 節税重視なら◎ |
6.3 家族全体での最適化
【4人家族の場合】
夫:1,800万円
妻:1,800万円
子1:1,800万円(18歳以降)
子2:1,800万円(18歳以降)
━━━━━━━━━━
家族合計:7,200万円の非課税枠!
第7章 実践シミュレーション
7.1 30歳から始める資産形成
前提条件
- 開始年齢:30歳
- 年間投資額:120万円(月10万円)
- 想定利回り:年5%
- 運用期間:35年
シミュレーション結果
| 年齢 | 累計投資額 | 評価額 | 使用枠 |
|---|---|---|---|
| 35歳 | 600万円 | 680万円 | 600万円 |
| 40歳 | 1,200万円 | 1,550万円 | 1,200万円 |
| 45歳 | 1,800万円 | 2,700万円 | 1,800万円 |
| 50歳 | 1,800万円 | 3,450万円 | 1,800万円 |
| 55歳 | 1,800万円 | 4,400万円 | 1,800万円 |
| 60歳 | 1,800万円 | 5,600万円 | 1,800万円 |
| 65歳 | 1,800万円 | 7,150万円 | 1,800万円 |
結果 1,800万円の投資で7,000万円超の資産形成が可能!
7.2 枠復活を活用した運用例
【50歳時点】
保有額:3,450万円(簿価1,800万円)
【戦略】
・生活費として年200万円取り崩し
・翌年、復活枠で200万円再投資
・実質的に配当のような仕組みを構築
まとめ 新NISAの1,800万円を最大限活用する
押さえるべき5つのポイント
- 1,800万円は保有限度額(生涯投資額ではない)
- 売却すれば翌年枠が復活(何度でも再利用可能)
- 簿価残高方式(評価額ではなく購入額で管理)
- 成長投資枠は1,200万円まで(つみたて枠は1,800万円OK)
- 家族で活用すれば効果倍増(夫婦で3,600万円)
今すぐ始めるアクションプラン
- 現在のNISA枠使用状況を確認
- 年間投資可能額を計算
- 5年後、10年後の目標設定
- つみたて/成長の配分決定
- 証券口座の開設・積立設定
新NISAの非課税保有限度額は、正しく理解すれば一生涯使える最強の資産形成ツールです。
この記事で学んだ知識を活かして、あなたも今すぐ資産形成の第一歩を踏み出しましょう!